このページは「表の使い方」と「現実の部屋に合わせた補正」を短くまとめています。基本の目標は冬の45〜50%RH。表で候補を選び、部屋の条件に合わせて少しだけ増減すると失敗しにくくなります。
表の見方(3ステップ)
- 部屋の広さを選びます(畳数/㎡)。
- 建物の条件を選びます(断熱・気密・築年など)。
- 目標湿度を45〜50%RHに設定し、表の加湿量(ml/h)帯から機種を選びます。
迷ったら一段上の能力を選び、日常は弱〜中の連続運転で使うと静音・省エネ・結露抑制のバランスが取りやすくなります(詳しくは加湿量の目安(解説編))。
加湿量の早見表
| 部屋サイズ | 木造(断熱弱) | 鉄筋(断熱良) |
|---|---|---|
| 6畳 | 400〜500ml/h | 250〜400ml/h |
| 8畳 | 500〜700ml/h | 350〜500ml/h |
| 10畳 | 700〜900ml/h | 500〜700ml/h |
| 12畳 | 900〜1200ml/h | 700〜900ml/h |
| 14畳 | 1200〜1500ml/h | 900〜1200ml/h |
現実の部屋に合わせる補正のコツ
- 天井が高い(2.7m以上):表の数値に+15〜30%を目安にします。
- 吹き抜け・開放間取り:隣室とつながる面積を考慮して+20〜50%。ドア開放なら上振れを想定。
- 築年数が古い・すきま風がある:外気の影響が強いので+10〜30%。
- 室内干し・調理が多い:水蒸気が加算されるため-10〜20%でも足りることがあります。
- 寒波・乾燥注意報:外気が極端に乾く日は先行運転を長めにし、能力は据え置き。出力で無理をせず気流づくりでカバー(サーキュレーター併用)。
方式ごとのざっくり傾向
超音波式は初動が速い反面、強出力にすると白い粉や床濡れが増えやすいので弱〜中が基本。
気化式は立ち上がりが遅い分、先行運転が効きます。
スチーム式は立ち上がりが速く能力も安定、就寝は弱固定+切タイマーで結露を抑えます。
ハイブリッド式は室温が安定したら気化寄りに切り替えると省エネです。
ケース別の読み替え例
- 8畳・築20年木造:表の「中〜やや高め」の帯を選び、弱連続で巡航。夜は目標湿度を少し下げると結露しにくくなります。
- 12畳・新しめのマンション:表の「中」帯で十分。先行運転を入れて強出力を避けると静かに保てます。
- 10畳・天井2.7m+室内干し:天井補正で+20%を見込みつつ、洗濯物が多い日は出力を一段下げて様子見します。
よくある勘違い
- 「強で短時間」のほうが効率的:結露・白い粉・床濡れの原因になりやすいです。弱連続+先行のほうが安定します。
- 自動任せでOK:夜間は機種により出力が振れます。就寝は弱固定+切タイマーが安全です(湿度の上がりすぎ回避)。
- 適用床面積=いつでも同じ:表示は理想条件の目安です。建物条件と季節で必要量は変わります。
関連:加湿量の目安(解説編) / サーキュレーター併用のコツ / 就寝時の加湿設定
よくある質問
「適用床面積」と「加湿量(ml/h)」どちらを重視すべき?
まずは加湿量(ml/h)を軸に選び、適用床面積は建物条件の目安として補助的に見るのがおすすめです。迷ったら一段上の能力を選び、日常は弱〜中の連続運転で静かに回すと失敗しにくいです(解説編)。
8畳と12畳で迷っています。どちらに合わせればいい?
断熱・気密や天井高で必要量が変わります。新しめのマンション8〜12畳なら「中」帯で足りることが多く、立ち上げは先行運転で強出力に頼らない運用が安定します。天井が高い/古い木造なら+15〜30%を目安に能力を上げてください。
吹き抜け・リビング階段です。どれくらい上乗せが必要?
空間がつながるほど加湿量が逃げるため、+20〜50%の上振れを見込みます。必要に応じて複数台の分散配置や、壁当ての最弱風で面拡散を作ると効率が上がります。
同じ加湿量でも方式で体感が違うのはなぜ?
立ち上がりの速さ(スチーム/超音波)や、均一性(気化/ハイブリッド+気流設計)、白い粉や床濡れの出やすさの違いが体感差になります。方式の特徴は方式別の選び方で整理しています。
1台大容量と2台分散、どっちが良い?
大容量1台は配線が少なく設置が簡単、2台分散はゾーニングしやすく冗長性があるのが利点です。電気代は運転モードの影響も大きいので、方式別の電気代も併せて検討してください。
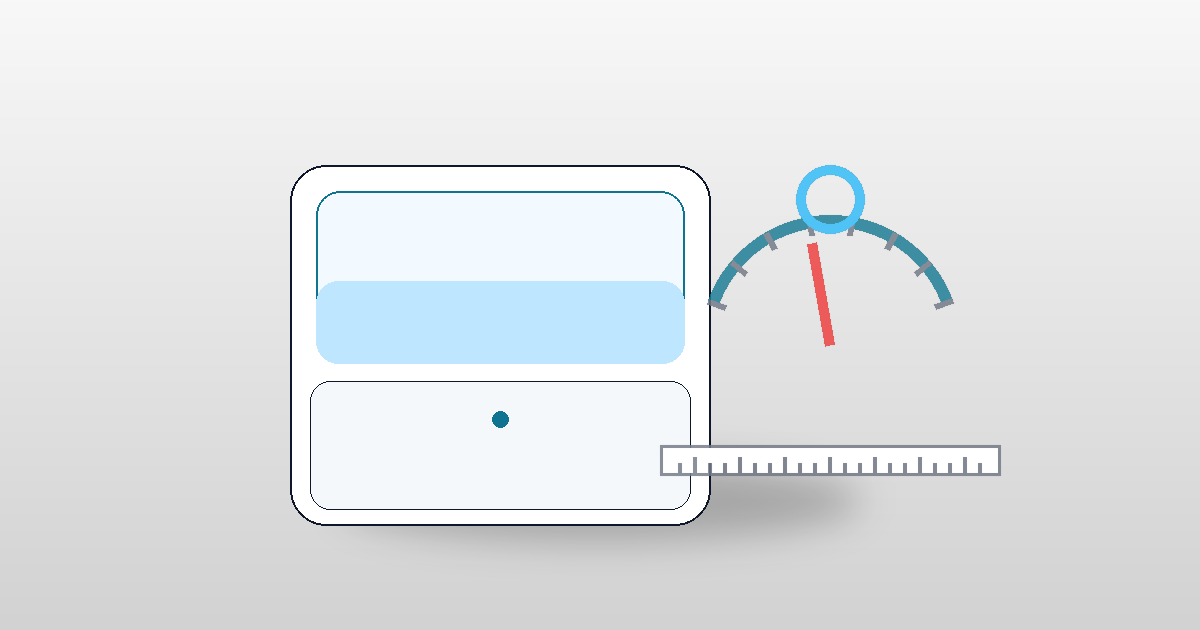


コメント